初級編1~50に引き続き、初級編 51~100をお送りいたします。
初級編 51~60
51.鎖場
険しい岩場に鎖が取り付けられた箇所のことです。
52.木道
登山道に木の板を敷いて植物などを保護しています。
53.丸木橋
沢を渡る場所などに丸太を使った橋のことです。
54.ガラ場・ガレ場
石の積み上げで敷き詰められている斜面のことです。
55.ザレ場
ガレ場よりも細かい石や砂で敷き詰められた斜面のことです。
56.浮き石
ガレ場やザレ場などで踏むと動いてしまう石のことです。
手を使うなどして慎重に通過することをお勧めします。
57.ラク!
自信が落石を起こしたり、発見した場合に大声で”ラク!”と言い周囲の登山者へ伝えることです。
58.悪場
滑落の危険がある岩場や鎖場、通行の難易度が高い場所のことです。
59.カール
丸い谷という意味で、氷河によって削られた跡がお椀状に抉れていることを言います。
涸沢カール(北アルプス)、千畳敷カール(中央アルプス)、仙丈ヶ岳カール(南アルプス)などが有名です。
60.U字谷
氷河によって削られた後にできた、大規模なU字形の谷です。
槍沢(北アルプス)などが有名です。
初級編 61〜70
61.氷河
標高の高い山に残っている雪が重みで圧縮され氷となり、時間をかけて流れ動いているものです。
62.雪渓
春や夏でも標高の高い谷に残っている雪のことを言います。
雪渓の上を登るのも登山の醍醐味の一つですが、中が空洞になっていたり、体制崩してどこまでも滑ってしまったりと事故も絶えないので要注意が必要です。
63.クレバス
基本、氷河の裂け目のことを言いますが、雪渓の割れ目のこともクレバスと言います。
64.湿原
低温で多湿な環境下で、淡水によって湿った草原のことを言います。
65.峠
稜線上で登りと下りの境目のところを言います。
峠には分岐だったり山小屋だったり休憩できる場所があります。
66.山小屋・ヒュッテ
山小屋とヒュッテはほぼ同じ意味ですが、登山者が有料で宿泊できる有人の営業小屋のことを言います。
67.避難小屋
緊急時に避難できるような無人の小屋のことを言います。
場所によっては宿泊や休憩ができる小屋もあります。
68.幕営(ばくえい)
テントで営むことを言います。
69.トレース
雪山で雪面についた先行者の足跡のことを言います。
70.エビのしっぽ
冬の標高の高い山で見られる霧氷の1種です。
木や岩などに風で吹きつけられて凍り、白いエビのしっぽのような形をしているのでこの名が付きました。
初級編 71〜80
71.吹き溜まり
風によって運ばれてきた雪が、深く積もっているところのことを言います。
72.ダイヤモンドダスト
雪山などで見られる空気中の氷の結晶が光と反射してきらきらと輝く現象のことを言います。
73.ホワイトアウト
激しい雪や霧の濃い場所で、空気と雪面との境目がわからないくらい視界が真っ白になることを言います。
74.樹氷
水蒸気が樹木に吹きつけられて、凍って全体を覆ってできることを言います。
蔵王の樹氷などが有名です。
75.フキノトウ
春になると地中から顔を出すフキの若い花茎のことを言います。
76.渓谷
山間の川や沢のことをいいます。
77.渓流
谷間に流れる川の流れのこと。
78.右岸・左岸
川や沢を上流から見て、右側が右岸、左側が左岸と言います。
79.右俣・左俣
川や沢を下流から見て、右側が右俣、左側が左俣と言います。
80.V字谷
川の侵食によって、深くえぐられた谷のことをいいます。
初級編 81〜90
81.峡谷
両側が険しく切り立った、岩壁に挟まれた幅の狭い谷のことをいいます。
黒部峡谷が有名です。
82.岩稜
岩でできた、急な尾根のことをいいます。
83.花崗岩
マグマが地下で固まり、石英と長石が主成分で比較的目の粗い岩石のことを言います。
北アルプスでいうと燕岳や烏帽子岳、南アルプスだと甲斐駒ヶ岳や鳳凰三山にある白い岩。
84.アタックザック・サブザック
今で言うULザックやトレランザックなどで、メインザックをデポして登攀用に使用するザックのこと。
85.ビブラムソール
現在販売されている、高い割合てこのビブラムソールが使用されており、足底に登録商標Vibramマークが入っております。
開発したイタリア人の名前の一部からこう名付けられています。
86.GORE-TEX(ゴアテックス)
さまざまな衣類や靴などに使用されている防水透湿素材のファブリック(生地)。登録商標されている。
87.ニッカボッカ
膝下までの半ズボンのことを言います。
現在はこのくらいの丈は主流ではなくなったが、昔は夏の登山のズボンといえばニッカボッカが主流だった。
88.スキットル
ウイスキーのようなアルコールを入れる、携帯サイズの金属製の容器のことを言います。
89.概念図
山の特徴を、尾根や稜線、山頂などを簡略化した地図のことを言います。
90.登山者カード・登山届
登山者の情報や緊急連絡先などを明記したカード(登山者カード)を登山する前に、地元の警察宛に提出をすること(登山届)。
初級編 91〜100
90.登山者カード・登山届
登山者の情報や緊急連絡先などを明記したカード(登山者カード)を登山する前に、地元の警察宛に提出をすること(登山届)。
91.ツェルト
軽量で小型の簡易的なテントのことを言います。
ビバークや休憩時などに活用します。
92.シュラフ
寝袋のことを言います。
93.コッヘル
アルミやチタン製の直火ができる容器(食器)のことを言います。
94.テルモス
携帯用の持ち運びできるような保温容器のことを言います。
95.ストック・トレッキングポール
トレッキングでバランスを取るために使う杖のこと。
これを使うこと全身の負担になり足の負担を和らげることができる。
96.エマージェンシート・サバイバルシート
アルミ製のシートで、保温や雨よけ、日除けができ、緊急時の待機や避難などに役立つ。
保温の場合は金色を表に、日除けの場合は銀色を表にする。
97.ランタン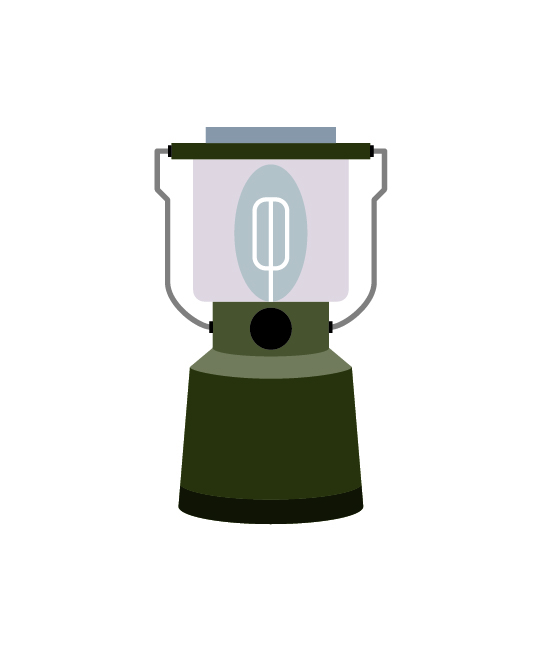
ガスや灯油を利用したランプのことを言います。
98.アイゼン・軽アイゼン
雪や氷の面を歩くときに滑らないためのスパイクで、登山靴の裏に装着します。
アイゼンは10~12本、軽アイゼンは4~6本の爪が付いています。
99.ピッケル
ヘッドは雪面を掘るもの、歩くとき雪面に突き立てるスピッツェ、それをつなぐシャフトの三つの部分からなる登山道具。
100.スノーシュー
深い雪でも歩行ができる歩行用具。
スノーシューでトレッキングを楽しむ方も増えてきています。
■登山に関する基礎的な知識はこちら
初級編 1〜50
初級編 101〜140
安全登山の基礎知識
■中級編
中級編 1〜50
■上級編
上級編 1〜40




コメント